WINCARS KURUMAYA KOZO くるま家Kozo 広島 舟入 輸入車 国産車 車検 メンテナンス
WINCARS KURUMAYA KOZO
〒730-0847
広島市中区舟入南4丁目8-14
TEL:(082)232-5200
FAX:(082)232-5199
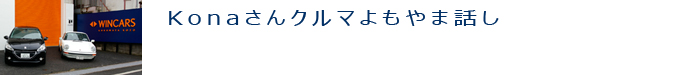
今日はちょっと暗い話を書きますね。
広島のアウトレットモールの広大な駐車場で車のイベントがあって
ルマン24時間で優勝したマツダの787など名車が集まるので行ってみてはと車屋さんにいわれましたが
ぼくは興味がありませんでした。六十年生きて日本のその種の雰囲気を知っているからです。
しかし偶然にもその日の朝、アウトレットモールの方面に用が有り時間も暇だったので
家に帰りかけたのをせっかくだからとUターンして行ってみました。
驚いたのは駐車場の車がマツダ車ばかり、これほどマツダの車を見たことがなく、内輪のイベントかと思ったくらいです。
欧州車はほぼ居なくて、ましてポルシェやロータスと言ったスポーツ車は一台も居ません。
しかしイベントではレーシングカーの787や初代のコスモなど美しい名車が並んで
オートバックスそのほか各社のブースなども出ていて大変な人だかりです。
でも家族連れやカップルはあまり居なくて雰囲気がオタクっぽく、やっぱりなあとぼくは思いました。
日本の文化が「カワイイ」と「オタク」であるといわれればそのとおりですが
じっさいにその雰囲気を感じるとすこし哀しいものがあります。
ありていに言えば、この異様さの中で日本の車は作られているのかと思いました。
人の群れから離れた会場の端に昭和三十年代R360や初代キャロル、ルーチェなど
ニューカーのような美しさで並んでいるのが見えて、資料として写真に残したいと思いましたが
カメラを持っていなかったぼくは携帯で写真を撮りました。
すると妙にぼくのほうばかり見ていた首から札をぶら下げた男が近づいて「関係者の方でしょうか」と言う。
きょとんとしていると「ここは一般の人は立ち入り禁止です」と言う。
「どこにも立ち入り禁止なんて書いてなかったよ」と言うと
男は憮然とした表情で「柵があるでしょう」と怒ったように言った。
言われて見ればそのとおりですが、どこからでも入れる隙間だらけの柵だから
ただの仕切りくらいにしかぼくは思わなかった。
口の聞き方を知らない人だなあと思い、「立ち入り禁止ならちゃんと表示しなきゃ分からないじゃない」と言うと
「一般の人はだれも入っていないから分かるでしょう!」と言う。
そういえば周りには首から札をぶら下げた人しか居ない。
あれだけの柵で一般のものが来ないというのが逆にぼくには不思議だった。
「これだけのイベントなのに地図の一枚もないし、どこがどうなっているのかさっぱり分からない。
プログラムもパンフレットもない。おかしいじゃない」とぼくが言うと
「わたしは関係ないので本部の人に言ってください」と言った。
なぜぼくが文句を言ったかといえば、ぼくはイベントに来た「客」であって主催者に気配りされなければならない立場だから。
「関係者」と「一般者」というくくりで一方的に悪いかのように言われてすこしカチンときたのです。
追い出されたぼくは「本部の人」を探し、傲慢な表情で席に座る五十代そのオジサンに同じ苦情を言うと、
彼はただ一言「申し訳ありませんね」と真摯さのかけらもなく言った。
長年ビジネスをしてきた常識人と思うぼくの考えではこのようなとき
分別ついたふうの「一般人」のクレームにすこしでも一理あるなら、やわらかな表情で
「それは気がつかなくてすみません。対処を考えておきますので」くらいのことは言うべきなのである。
そもそも彼も、そしてぼくが写真を撮っていたときに注意した男も広島の人ではないかもしれない。
なぜかと言えば、ひとりくらい不注意なものが居て写真を撮っていても、状況として何の問題もないなら
まして関係者に見えなくもない雰囲気のぼくであるなら広島流では見守るだけにしておくだろうから。
ルマンの787のエンジン音を聞きたくもあったが、そういうイベントがあるのか
あればいつなのか、「関係者」に聞くのも面倒で会場の雰囲気も嫌だからぼくは早々に退散しました。
日本の自動車を巡る環境の一面について書きたかったのです。このイベントがマツダ本社と関連があるのか知りませんが
もしも日本車、あるいはマツダの車にどことない暗さがあるとするなら、こういうことなのでしょうね。
マツダは海外の観光客多い広島の市街地にしゃれたミュージアムやちょっとしたスペースくらい展開しても良い
というより絶対にすべきなのですが、それのできないところに社風の限界があるようにぼくはつねづね思っていました。

